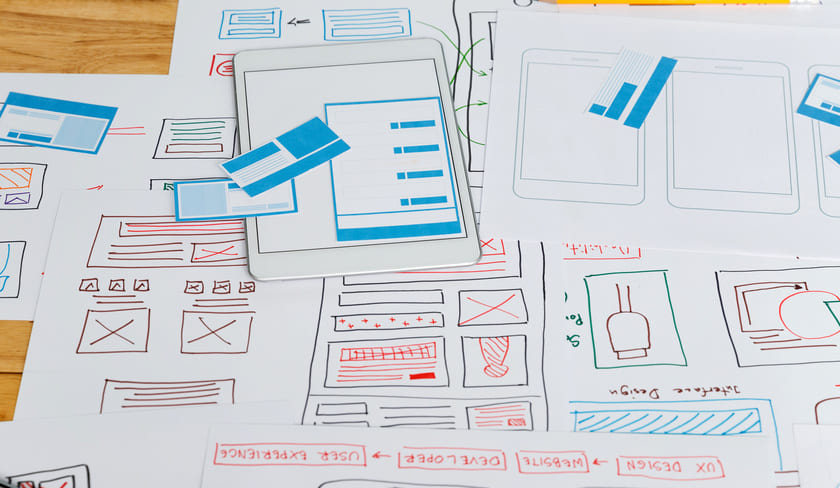WEBデザインのみを依頼したい方へ 相場や選び方のポイントを解説

Webサイト制作を自社で進める中で、「デザインだけ外注したい」というケースがあります。
しかし、デザインだけ委託できるのか? 委託する場合にどのような注意点があるのか?という疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、Webデザインのみを依頼する方法について、そのメリット・デメリットや費用相場、適切な依頼先の選び方から注意点まで詳しく解説します。
社内の開発リソースを活用しつつプロのデザインを取り入れたいとお考えの企業担当者様は、ぜひ最後までご覧ください。
Webデザインのみの依頼とは?
Webデザインのみの依頼とは、ホームページ制作工程の中でデザイン作業だけを外部に委託することを指します。
通常はサイトの企画設計からコーディングまでを一括して依頼しますが、自社でコーディングなど他の工程を対応できる場合に、この方法を取ることで専門的なデザイン力を確保しつつ開発全体のコストを抑えることが期待できます。
Webデザインのみを依頼するメリット
Webデザインのみを依頼するメリットは、必要な業務だけ外注することでコストを省き、自社リソースを有効活用できる点にあります。
デザイン作業を専門家に任せることで品質の高いビジュアルを得られ、同時にコーディングなどは社内で行うため外注費用を抑えられます。
以下では具体的なメリットとして、「外注費を抑えられる」ことと「社内のコーディングスタッフを活用できる」ことの2点を解説します。
コストを抑えられる
コストを抑えられるとは、Webサイト制作を全て外注する場合よりも、デザイン工程だけを切り出して依頼することで予算を低減できることを意味します。
デザインのみを発注すれば、開発や実装にかかる費用を外注先に支払う必要がなくなり、その分コスト削減につながります。
結果として、限られた予算内でもプロのデザインクオリティを導入しやすくなるのが大きなメリットです。
社内のコーディングスタッフを活用できる
社内のコーディングスタッフを活用できるとは、デザイン以外の実装部分を自社のエンジニアで対応することで、社内人材の能力を有効に生かせる状態を指します。
自社に開発担当者がいる企業であれば、デザインのみ外部委託しコーディング作業は社内で行うことで、社内スタッフの稼働機会を確保できます。
こうすることで外注コストを下げられるだけでなく、自社メンバーがサイト構築に深く関与するため、最終成果物への理解も高まります。
Webデザインのみを依頼するデメリット
Webデザインのみを依頼するデメリットとして、対応してくれる依頼先が限られることや、後工程での調整負担が増えることが挙げられます。
デザイン専門での外注は魅力的ですが、その分課題も存在するため、事前に理解しておくことが大切です。
以下に代表的なデメリットとして、「デザインだけを受けない制作会社がある」ことと、「動きのある部分はコーダーとのすり合わせが必要になる」ことを説明します。
デザインだけを受けない制作会社がある
多くの制作会社はWebサイト全体の制作案件を前提としているため、デザインのみの小規模案件は採算が合わず受け付けてもらえないケースがあります。
また、デザイナーの稼働がいっぱいになる一方、コーダーの稼働率が落ちてしまう可能性があるため、リソースのバランスの問題で引き受けないケースもあります。
その結果、デザインのみを引き受けてくれる制作会社や専門デザイナーを探す工数がかかってしまうため、その手間がデメリットと言えます。
動きのある部分はコーダーとのすり合わせが必要になる
動きのある部分はコーダーとのすり合わせが必要になるというのは、アニメーションやスライダーなど動的な表現を伴うデザインの場合、デザイナーとコーダー間で実装方法の調整が欠かせないという意味です。
例えば、ボタンのホバー時のエフェクトやスクロールに応じたアニメーションなどは、デザイナーの意図を正確にコーダーに伝えないと、完成したサイトでイメージ通りに動作しない恐れがあります。
このように、デザインと実装を別々に行う場合は両者の連携に手間がかかり、特に動的機能の多いサイトではその調整負担がデメリットとなります。
また、そのすり合わせの工数を避けるため、デザイナー側が動きのないデザインを採用してしまい、シンプルなデザインになる可能性もあります。
Webデザインのみ依頼時の費用相場
Webデザインのみ依頼時の費用相場とは、Webサイトのデザイン作業だけを外注する際に一般的に発生する料金の目安です。
依頼する範囲やサイト規模、依頼先の種類(制作会社かフリーランスか)によって費用は変動しますが、ここでは代表的なケースごとの相場観を解説します。
ホームページ全体のデザインの費用相場
サイトのページ数や内容によって大きく異なりますが、小規模なコーポレートサイトであればデザイン費用は概ね約10万~30万円程度に収まり、中・大規模サイトでは約50万~数百万円となるケースもあります。
トップページのデザイン相場
一般的には簡易なトップページデザインであれば数万円程度から依頼可能ですが、凝ったビジュアルや特殊な演出を盛り込む場合は約20万~50万円と高額になることもあります。
規模や求める品質に応じて適切な依頼先を選ぶことが重要です。
下層ページのデザイン相場
下層ページのデザイン相場とは、トップページ以外の各下層ページ(サービス紹介や会社概要ページ等)を1ページ単位でデザイン依頼する場合のおおよその費用目安です。
下層ページのデザイン費用はトップページに比べると低めで、一般的に1ページあたり約数万円程度が相場となります。
これは下層ページがトップページのデザインテイストや定義を踏襲して作成するケースが多いため、1ページごとのデザイン工数が抑えられるからです。
具体的には、シンプルな内容の下層ページであれば1ページあたり約2万~5万円程度、情報量が多いなど、個別に凝ったデザインが必要なページでも約8万~10万円前後が一つの目安です。
バナーデザインの相場
一般的な静止画バナーであれば1枚あたり約数千円〜1万円程度で、キャンペーン広告など大きめのバナーでは1枚あたり約2万〜3万円前後になることもあります。
また、GIFアニメーションなど動きのあるバナー制作はさらに料金が上がり、数万円台に達するケースがあります。
Webデザインのみの依頼先の選び方
Webデザインのみの依頼先の選び方とは、デザイン業務だけを外注する際に、どのような相手(制作会社またはフリーランス)に依頼するのが望ましいか、その判断基準のことです。
デザインのみを任せる場合、主な選択肢としてWeb制作会社に依頼するか、フリーランスのデザイナーに依頼するかが挙げられます。
それぞれメリット・デメリットが異なるため、自社の状況や求める条件に照らして最適な依頼先を選ぶ必要があります。 以下では、「制作会社にWebデザインのみを依頼する場合」と「フリーランスにWebデザインのみを依頼する場合」のそれぞれについて、考えられる利点と注意点を整理します。
制作会社にWebデザインのみを依頼するメリット・デメリット
制作会社に依頼するメリット
制作会社には経験豊富なデザイナーが複数在籍しているため、プロのチームによるクオリティの高いデザインが期待できます。
また、社内にディレクターやプロジェクトマネージャーがいるため進行管理が行き届き、納期遵守や品質管理の面で安心感があります。
制作会社に依頼するデメリット
一方で、制作会社はフリーランスに比べて料金が割高になる傾向があります。
組織として運営している分、間接費用やマージンが価格に反映されるため、同じ内容のデザイン依頼でも費用負担は重くなりがちです。
また、前述の通りデザインのみの小規模案件自体を受け付けていない制作会社も少なくありません。
そのため依頼先候補を見つけるのに時間がかかるなど、希望する会社が対応不可であるケースもデメリットと言えます。
フリーランスにWebデザインのみを依頼するメリット・デメリット
フリーランスにWebデザインのみを依頼するメリット・デメリットとは、個人のWebデザイナーにデザイン業務だけを発注した場合に得られる利点と懸念点のことです。
フリーランスに依頼するメリット
フリーランスに依頼する最大のメリットは、費用を比較的抑えられる点です。
一般的にフリーランスのデザイナーは制作会社よりも経費が少ないため、同じ作業でも割安な見積りとなることが多く、中小規模の案件では特にコストメリットが顕著です。
また、個人で柔軟に対応できるため細かな要望にも融通が利きやすく、直接デザイナー本人とやり取りできることでイメージの共有や修正依頼もしやすいという利点もあります。
フリーランスに依頼するデメリット
反面、フリーランスはスキルや経験値が人によって大きく異なるため、依頼する相手を見極める必要があります。
実績が乏しい相手に依頼した場合、思ったようなクオリティにならないリスクもゼロではありません。
過去のポートフォリオなどの実績を見ても、全部に関わったのかまで分からないため、クオリティの判断は非常に難しくなります。 また、個人ゆえに作業負荷や予期せぬ事態で納期遅延になるほか、場合によっては連絡不能になるリスクがあり、サポート体制も企業に比べ手薄である点がデメリットです。
Webデザインのみを依頼する際のチェックポイント
Webデザインのみを依頼する際のチェックポイントとは、デザインだけを外注するにあたって事前に確認・準備しておくべき重要事項のことです。
スムーズにプロジェクトを進行させ、後からのトラブルを防ぐために、以下の点を発注前にチェックしておきましょう。
Webサイト全体の構成の提案ができるか
Webサイト全体の構成の提案ができるかとは、貴社の強みを把握し、何をどのように訴求すれば良いかを理解した上で、それをページ構成、サイト全体の構成に落とし込む提案ができるかどうかを指します。
これは、これまでのWebサイト制作の実績が豊富であるなど、実際に売上アップに貢献してきた経験がないとできません。
Webサイトの目的は集客であり、売上アップであるため、この点を満たせるかどうかは非常に重要なポイントです。 逆に、見た目だけに終始する相手だと、サイト全体の使い勝手や目的達成に支障をきたす恐れがあります。
実績と経験が豊富
実績と経験が豊富かどうかとは、発注候補のデザイナーまたは制作会社がこれまでに多数のWebデザインプロジェクトを手掛けてきており、一定の成果を上げているかを示す評価ポイントです。
豊富な実績を持つ相手は、様々な業種やサイト規模でのノウハウが蓄積されているため、デザインの質や対応力において信頼感があります。
特に、自社が属する業界や類似するコンセプトのサイト制作経験があれば、業界特有のニーズやデザインのツボを理解している可能性が高いでしょう。 一方、経験の浅いデザイナーだと提案力や問題解決力に不安が残る場合もあるため、事前にポートフォリオや過去の事例を確認し、実績の程度を見極めることが大切です。
コミュニケーションがスムーズ
デザイン外注では初期ヒアリングから修正依頼まで多くのやり取りが発生するため、意思疎通が滞りなく進む相手かどうかはプロジェクトの成否に直結します。
問い合わせへの回答が遅く要領を得ない相手だと、修正のたびにストレスを感じプロジェクトに支障が出る恐れがあります。
逆にコミュニケーションが円滑な相手であれば、修正の手戻りも減り納期遵守もしやすくなるため、重要なチェックポイントです。
SEOやUI/UXに強い
SEOやUI/UXに強いとは、外注先のデザイナーが検索エンジン最適化(SEO)やユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス(UI/UX)の知見を持ち、デザインに活かせることを意味します。
単に見栄えが良いだけでなく、サイト訪問者にとって使いやすく目的を達成しやすいデザインになっているか、また構造的に検索エンジンから評価されやすい設計になっているかは重要なポイントです。
例えば、ページの読み込み速度に配慮した画像や構成、見出しやテキスト配置が論理的でSEOキーワードを活かしているか、といった点はプロのデザイナーでも意識の差が出ます。
これらに精通したデザイナーであれば、デザイン面と同時にサイトの集客力やユーザビリティ向上にも貢献してくれるでしょう。
使用ツール(Figma, XDなど)の確認
使用ツール(Figma, XDなど)の確認とは、デザイン制作にあたって用いるソフトウェアやツールが何であるかを事前に把握し、納品データの形式や自社側での扱いやすさを確認することを指します。
近年ではFigmaやAdobe XD、SketchなどWebデザイン用ツールが多様化しており、依頼先と自社で使用ツールが異なるとデータ受け渡しに支障が出る可能性があります。
例えば、自社のコーダーがFigmaでデザインカンプを閲覧・コーディングする場合、デザイナーもFigmaで制作できるか確認が必要です。 ツールが合わなければ変換の手間やレイアウト崩れのリスクが生じます。
Webデザインのみを依頼する際の注意点
Webデザインのみを依頼する際の注意点とは、デザイン部分の外部委託を進める上で特に気を付けておきたい事柄のことです。
事前に注意点を押さえて対応することで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズなプロジェクト進行が期待できます。
以下に主要な注意点を4つ挙げ、それぞれについて解説します。
契約前に発注内容を明確にする
契約前に発注内容を明確にするとは、依頼するデザイン業務の範囲・内容を契約締結前に双方で具体的に定義し、共通認識を持っておくことを意味します。
Webデザインのみを発注する際には、どのページをどこまでデザインするかやワイヤーフレーム準備の有無、レスポンシブ対応の要否など、依頼範囲を細部まで双方で擦り合わせておく必要があります。
契約書に作業範囲と成果物を明記し、双方が納得した上でプロジェクトを開始すれば、認識違いによるトラブルを防ぐことができます。
デザインデータの所有権を確認する
デザインデータの所有権を確認するとは、完成したデザインの著作権や使用権がどちらに帰属し、どう利用できるかを事前に取り決めておくことです。
自社で今後デザインを改変・更新する予定があるなら、元データ(編集可能ファイル)を受け取れるよう交渉しましょう。
コーディング担当者との連携体制を確立する
コーディング担当者との連携体制を確立するとは、外注したデザイナーと実際にサイトを実装する社内または外部のコーダーとの協力関係を構築し、情報共有を円滑にすることを指します。
デザインとコーディングの担当が別の場合、実装段階で齟齬が生じないよう早い段階から両者が情報共有できる体制を作っておきましょう。
デザイン確定前にコーダーへデザイン案を共有し、技術的に難しい部分は調整するなど事前の打ち合わせが有効です。
また、デザインデータの連携時にはコーダーが必要とする画像やスタイルガイドがきちんと揃っているか確認し、受け渡し方法を明確に決めておくことも大切です。
修正回数や追加料金の有無を確認する
修正回数や追加料金の有無を確認するとは、デザイン制作途中および納品後の修正対応が何回まで契約料金内に含まれるか、また規定を超える修正や要件追加に対して追加費用が発生するかどうかを把握しておくことです。
多くの場合デザイン修正は2〜3回まで基本料金に含まれますが、それ以上は追加料金となるケースがあります。
修正対応の範囲と回数のルールを事前に確認しておけば、想定外の費用増加やスケジュール遅延を防げます。
また、デザイン完了後にページ追加など当初範囲外の依頼が発生した場合の料金についても、契約前に取り決めておきましょう。
Webデザインのみの依頼でお困りの方へ
Webデザインのみの依頼でお困りの方、あるいは外注先選びに悩んでいる場合、Webサイト制作やマーケティングの実績が豊富な会社に相談してみましょう。
例えば、リバミーでは、Webデザインのみの依頼にも柔軟に対応し、プロジェクト全体を視野に入れた提案を行っています。
リバミーの強みは、Webサイト制作から集客支援、エンジニア派遣までIT領域をトータルにカバーできる点にあります。
そのため、デザイン単体の発注であっても、必要に応じてディレクターやコーダーを含めた支援を受けることが可能で、デザインと実装のミスマッチを防ぐ体制が整っています。
また、同社には経験豊富なデザイナーが揃っており、内部の育成システムも充実しているため、常に一定以上のクオリティを担保できるのも安心材料です。
コスト面でも、社内リソースの効率運用によって高品質なサービスを適正価格で提供しているとの評価があります。
Webデザインのみの依頼で何から始めればよいか分からない、信頼できるパートナーが見つからないといった場合は、リバミーのような実績ある企業に一度相談し、自社の課題や希望をぶつけてみるとよいでしょう。
「信頼」を大切に掲げるリバミーでは、ヒアリングを通じて最適な解決策を提案しているため、デザイン外注に関する不安のほとんどが解消されます。
まとめ
Webデザインのみの依頼は、コスト削減や自社リソース活用といったメリットがある一方で、依頼先が限られることや進行面の課題などデメリットも存在します。
そのため、発注前にメリット・デメリットを正しく理解し、自社の状況に合った外注先を選定することが重要です。
依頼後も、発注内容の明確化、権利関係の確認、関係者間の連携強化、そして契約条件(修正ルール等)の事前確認という4つの注意点を意識して進めることで、トラブルを防ぎ円滑な制作が可能になります。
もし依頼先選びに迷ったら、実績豊富で信頼できるパートナー企業に相談することで、不安を解消しつつプロジェクトを成功へ導くことができます。
以上、Webデザインのみを依頼する際のポイントと知識を参考に、効果的な外注活用にお役立てください。